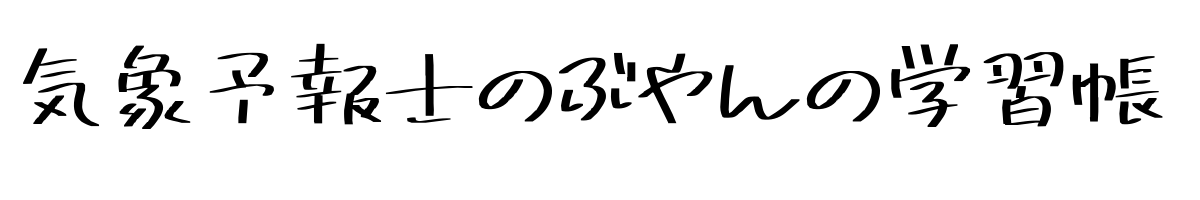朝起きて、庭の草に雫が沢山ついているときってありますよね。
あの雫が露(つゆ)になります。
さらに良く冷えた朝には霜が降りてたりします。
霜や露はどんなものなのか?どんな気象条件にできるのか?解説していきます。

僕の簡単なプロフィールです。
- 気象予報士
- 福岡あたりの気象のこと中心になりがち
露(つゆ)ってなに?

晴れた風もほとんど吹かない夜は、放射冷却がよく効いて地表面付近はよく冷えます。
地表面がよく冷えたら、冷えた地表面に接する空気も冷やされます。
空気が冷やされると気温が露点に達します。
空気中の水分が凝結して出てきた水滴が露(つゆ)です。
露は冷えた地表面付近にある草の葉に付着しやすいです。
物に露がつくことを結露(けつろ)といいます。
また、露ができたのちに気温が氷点下に下がったら露が凍結することがあります。これを凍露といいます。
露ができやすい気象条件
露は、曇りで風の強い日よりも、良く晴れた風がない夜に放射冷却が効いて発生しやすいです。
このような気象条件になりやすいのは、高気圧圏内のときですね!
天気のことわざで「朝露が降りると晴れ」といったりするのもこのためです。
(朝の露を朝露といったりします。)
また、俳句の季語で露は秋の季語とされていますが、秋は移動性高気圧がやってくる季節です。
日中ぐんぐん気温があがって、夜は放射冷却でがんがん冷えるので露は発生しやすいですよね。
霜(しも)ってなに?

霜も、露と同じく晴れた風がほとんど吹かない朝に発生します。
放射冷却によって地表面が良く冷えて、地表面に接する空気が冷やされるところも同じです。
霜と露とが決定的に違うのは、露点に達して凝結した水滴が露なのに対して霜は露点温度が氷点または氷点下のときに形成されます。
水蒸気が昇華によって、氷の結晶をつくるのです。
霜ができやすい気象条件
露と同じく、良く晴れて風がほとんどない夜に放射冷却がきくときに発生します。
なので高気圧に覆われるような時には発生しやすいことになります。
露と霜で違うのは、露点温度が氷点・氷点下に達しているかどうかってことですね。
露と同じく霜は天気がよいサインといわれていて「霜が降りると晴れ」といわれたりします。
(おまけ)霜と露と霧との違い
露や霜は、良く晴れて風が風がほとんどない放射冷却がよくきく夜に地表面付近で形成されます。
地面付近の浅い層でできます。
霧(きり)の場合は、地表面の厚い層が冷えて露点温度に達した時には水滴(雲粒)として凝結することになります。
霧も地面付近の現象です。
霧の方が厚い層であるのに対して、霜や露はごくごく地表面の浅い層でできるものになります。
まとめ
今回の内容についてまとめました。
- 露は空気が冷やされて凝結した水滴のこと
- 霜は空気が冷やされて水蒸気から昇華した氷の結晶のこと
- 良く晴れて風がほとんどない放射冷却がよく効く夜に発生しやすい
- 霜・露ができやすいのは高気圧におおわれているとき
以上が、霜(しも)と露(つゆ)ってどんなときにできるのか解説します。でした。
読んでいただきありがとうございました。